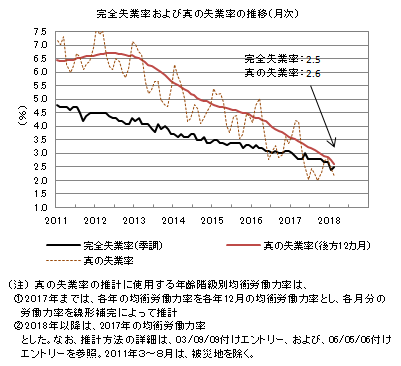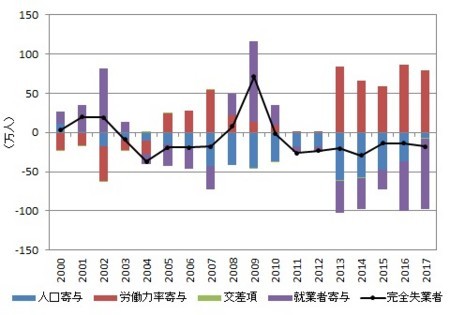著者は、大阪ガスで各種課題解決支援を手がける分析専門組織ビジネスアナリシスセンターの所長で、日経情報ストラテジー「データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー」の初代受賞者(2013年)。米国の研究所でデータ分析に従事した経験があり、2005年には大阪大学で博士号(工学)を取得、神戸大学経済学部の講師も務める。
本書で著者が一貫して主張するのは、ビジネスデータ分析を行う上で分析者が持つべきマインドであるが、分析者に限らず、むしろビジネスに携わる者すべてが参考とすべきものであるとの印象を受けた。「はじめに」で、著者はその経験をつぎのように述べる。
じつは私も、10年前まではデータ分析=数値計算ぐらいに思っていました。社内ではデータ分析のエキスパートのようにみなされ、「彼に頼めばどんなデータ分析もやってくれる」と重宝がられました。
しかし、あるときに「お前はまるでデータ分析の便利屋だな」と言われてから、自分の存在意義について疑問を持つようになりました。そんなとき、米国ローレンスバークレー研究所で仕事をする機会に恵まれました。黙々とデータ分析をこなす私に対して、米国人上司から「私はあなたに数値計算を期待しているのではない。分析を期待しているのだ」と諭されました。それを機会に、データ分析に関する考え方が大きく変わりました。それまで、データ分析の主役は高度な数値計算と思っていたのですが、それらは手段に過ぎない、単純な集計で十分ならばそれでいい。大切なのは、意思決定に役立つことなのです。それまで、周囲から便利屋扱いされていた理由もわかりました。私は、データ分析の仕事をしていたのではなく、データ分析に必要な行為(数値計算)を得意としているに過ぎなかったのです。
前述のマインドが生まれた背景には、こうした異文化との接触があったことがわかる。この後、一貫して主張するのは、いずれも「市場」というか、そうした場での他者との接触において生じ得るマインド・セットであり、(日本的な)組織の内部からは、(それ自体、単純なものであっても)なかなか見えてこないもののように思える。
分析の「価値」とは?
著者はまず、分析の「価値」をつぎのように整理する。
「分析の価値」=「意思決定への寄与度」×「意思決定の重要性」
意思決定とは、「経営、投資、営業、調達、オペレーションなどあらゆる局面における意思決定」を指す。高度な分析手法や大規模なデータを扱うことは、それ自体、価値を持つわけではない。投資額が巨大であるなど重要な意思決定において、分析結果が重要な材料とされることで、始めて価値を持つことになる。価値ある分析結果を作り出す上で分析者に必要なことは、①ビジネス課題を見つけ、②データ分析で分析課題を解き、③数値解をビジネスの意思決定において使わせることである。本書の第2章では、そのために必要な能力について具体的に論じられ、さらに第3章では、正しい心構えや習慣付けが論じられる。
ビジネス課題を解くことの正しい動機付けは、意思決定を支援することであり、一方で例えば「特定の意見を支持すること」は、間違った動機である。そうした場合、分析者は正に前述の「便利屋」に陥ることとなるだろう。
たとえば、投資判断のためのデータ分析において、あらかじめ投資することは決めており、それを正当化するために分析をする。たとえば、販売量予測において、増加傾向になるような結果のほうが上司にほめられるので、増加傾向になるような結果を出すよう分析する。これでは本末転倒です。悩ましい意思決定を決めるためにデータを分析するのに、すでに意思決定が決まった後で、データ分析をするのですから。
さらに、分析者が持つべき良い習慣づけとして、以下の九ヵ条をあげる。
- ビジネスの現場に出て、ビジネス担当者とコミュニケーションすることで、「チャンス」、「ヒント」、「ゴール」を見つけることができる
- 整理整頓を心がける
- ちょっとした質問を投げかけることで、分析者自身「分析ストーリー」が明確に描けているかがわかる
- データをビジュアル化する(結果の数値だけで判断しない)
- 他人のデータを疑う
- 単純なほどすばらしい
- 「ざっくり理解」ができるようになる*1
- 文章を書く(プレゼンテーション用の資料だけでは、「理解した気分」だけになる可能性)
- うまくいかなければ、分析の「目的」に立ち返る
分析モデルの限界
本書は、こうした分析者が持つべきマインドに関する内容が大宗を占めるが、分析結果をみる上で重要なポイントもいくつか述べられる。まず、どんな分析でも「分析モデル」を使うが、これは現実の問題を単純な問題に変換したものであり、数値計算結果の解釈を通じ、現実世界における解が導かれる。分析者は、分析モデルがどのような前提に立っているか、常に意識する必要がある。また、分析モデルから現実を再現することはできない。
分析モデルに関する最大の勘違いは、分析モデルを作り込めば現実をほぼ再現できるという思い込みです。エマニュエル・ダーマンは、著書”Models. Behaving. Badly.”の中で、分析モデルを模型飛行機のようなものと表現し、多くの分析者は、分析モデルという模型飛行機と実際の飛行機を区別できていないと述べています。分析モデルとは、プラモデルのようなものに過ぎないのです。
また、データ量が増えることだけでビジネスイノベーションを起こせるようになるわけでもない。ビッグデータもまた「いわば表面は実物と同じくらい精巧だが中身は空洞のプラモデル」に過ぎない。
ビクター・マイヤー=ショーンベルガーとケネス・クキエは、著書”Big Data : A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think”の中で、ビッグデータの本質について、「部分計測から全数計測へ(from some to all)」という言葉で言い表しています。従来は、大量のデータを扱えなかったので、母集団の一部だけをサンプリングしてデータを計測していました(部分計測)。現在は、大量データを扱えるので、母集団のすべてをデータ計測できるのです(全数計測)。(中略)
たとえば、顧客に推薦する商品を決める場合、部分計測の世界では、アンケート調査などにより、「年齢が上がると、商品Aよりも商品Bを好む傾向にある」「所得が増えると、商品Cよりも商品Dを好む傾向にある」などの因果関係を検証し、それに従って顧客に推薦する商品を決めてきました。一方、全数計測の世界では、顧客間で購買行動の類似度を検証し(相関分析)、ある顧客に推薦する商品を決める場合には、その顧客と購買行動が類似している顧客が購買している商品とすれば良いのです。アマゾンは、この方法で顧客に商品を推薦し(リコメンデーション機能)、売り上げを伸ばしているのです。
(中略)但し、因果関係はわかりません。予測や判別の精度と分解能は高くなりますが、その根拠はわからないのです。
さらに言えば、ビジネス課題の解決にデータ分析を用いる場合、そもそもデータの存在を認識する必要がある。著者によれば、活用できる(社外)データは増え、その収集コストも低下しているとのことであるが、分析者にとっては、データの存在を認識し、アクセスできるようにすることもまた最初の一歩であり、このことが「躓きの石」となる可能性もあるだろう。