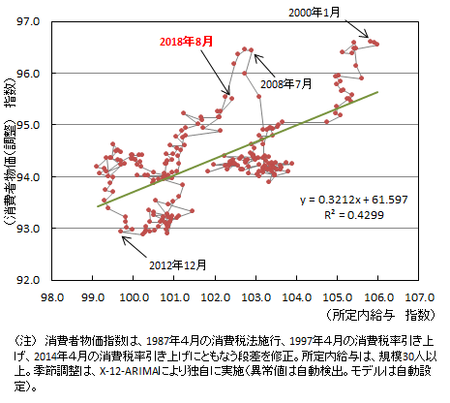- 作者: 小島寛之
- 出版社/メーカー: 青土社
- 発売日: 2018/09/19
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
2014年に亡くなった日本の大経済学者、宇沢弘文に対するオマージュ的書籍。「二部門経済モデル」など、宇沢の新古典派経済学者としての主要業績についても触れられているが、主として、「社会的共通資本」をめぐる思想的な側面が中心に語られ、特に、著者自身との出会いと経緯については、多くが語られている。本書の全体において「先生」という敬称が用いられ、著者がいかに宇沢に対し思いを抱いていたかが偲ばれる。後半を中心に、宇沢理論を継承する新たな潮流として、小野善康のマクロ経済モデル、松井彰彦の帰納的ゲーム理論、ボウルズの選好の内生化に関する理論が取り上げられている。
新古典派から社会的共通資本へ
第2章「宇沢弘文は何を主張したのか」では、宇沢が新古典派経済学から社会的共通資本を中心とする宇沢理論へと舵を切った理由として、「新古典派の数学的な枠組み自体が、演繹できる帰結を限定的にしてしまい、それが現実の経済現象と相容れないこと」、「新古典派の枠組みの持つそのような限定的性質を極端な形で乱用」する傾向が新古典派経済学の中にみられ、反社会的(と宇沢自身が考える)帰結を量産していることを上げている(p.40)。前者に関して具体的にみると、「時間」をめぐる次元の問題と、「実数論」の基数的性質の問題が重視されている。
新古典派の理論は「可塑性」の概念を持ち、資本は時間をかけずにどんな財にでも変化できる。これは見方によれば、資本の量をその変化率、すなわちその時間微分という異なる次元に属するものと同一視している、ということである。また、アローとドブリューが完成させた一般均衡理論は、数学における不動点定理と「同値」であり、そのことを宇沢自身が証明している。この場合、「実閉体(実数の世界と思えばいい)のモデルでは、どんな問題も「決定論的」である」という実数論としての帰結の限定性に、一般均衡理論が縛られていることになる。
これらの指摘は、賛否はどうあれ、大いに興味を引くものではないかと思う。
社会的共通資本と数学
一方で、第3章「社会的共通資本としての数学」では、そこから更に踏み込んで、数学が持つ社会的共通資本としての性質と、数学を忌み嫌うがゆえに低い階層の属性を受け入れてしまう一群の人々がいることについて、ボウルズとギンダスの理論をもとに論じられる。
社会的共通資本について、著者は「自然環境や公共インフラ、医療制度や教育制度のように、人間の生活に欠かすことのできない基礎的装置であり、また、基本的人権に関与することから、市場取引に委ねることが許されない資本の総称」(p.45)と整理している。著者は、数学の社会的機能を本来性、言語性、歴史的伝承性、地域文化性、技術性という5つの言葉で整理し、それが社会的共通資本の持つ性質と共通している点から、数学は社会的共通資本であると位置付ける。
ところが現実には、数学は「選抜」の目的で受験競争に用いられるなど、人間が(日常言語と同様)先天的に備え持つという本来性に依拠するものとは異なる使われ方をしている、と著者は指摘する。特に、数学オリンピックについては、「「選民」的な発想を持つ」との厳しい言葉を投げかけ、財団の姿勢にも批判的である。このような著者の数学に対する視座は、本稿の筆者にとっては極めて強く違和感を持つところであるが、このことについて論じるのは内容紹介という本稿の趣旨を超えるため、稿を改めて触れることとしたい。
宇沢理論を継承する新たな潮流
宇沢理論を継承する新たな潮流として、小野善康のマクロ経済モデル、松井彰彦の帰納的ゲーム理論、ボウルズの選好の内生化に関する理論が取り上げられていることは既に述べた。このうち、いわゆる「小野理論」については、本ブログの中でも過去に何度か取り上げた*1。ここでは、帰納的ゲーム理論と選好の内生化について触れ、宇沢と著者が共有する思想の核心が何処にあるかについて、思うところを述べておく。
通常の非協力ゲームでは、確定したゲームの構造から演繹的に戦略が作られるが、帰納的ゲーム理論では、プレイヤーが「空想上のゲーム」をプレイしながら行動し、知識を構築する。そうした過程から、差別や偏見が生まれることが、具体例をもとに論じられている。選好の内生化に関しては、インセンティブを付与することが新古典派経済学における帰結とは異なる帰結をもたらすことがある、というボウルズの議論が取り上げられている。
こうした議論をもとに推論を進めると、人間が持つ本来性とは関係なく、社会におけるゲームの仕方が差別や偏見を生み出し、あるいは帰納的に構築されたゲームのルールによって「選抜」的な状況が生じ、社会の中に「格差」が生じるという一種の社会観が生まれる。実際、帰納的ゲーム理論を研究する松井彰彦による「障害」についてのつぎのような見方が紹介されている。
すなわち、「障害」というのは、絶対的に固有に存在している身体状態というのではなく、社会通念によってフィードバックされる「関係性の問題」である、ということだ。(p.88)
この議論をさらに敷衍すれば、能力、数学の出来・不出来といったものも、人間の本来性とは関係がない、社会が作り出したある種の見方に過ぎない、ということになるのかも知れない。数学的能力は、人間に「プレ・インストール」された能力であり、人間にとって本来的なものであるが、そこから「格差」を生み出しているのは、社会における関係性だ、ということなのだろう。こうしたところに、宇沢と著者が共通して持つ社会思想的側面があるように思われる。
しかし、こうした考え方において、例えば特殊な数学的才能者などの“the gifted and talented”は、どのように位置付けられてしまうのか、悪平等的に標準化された公共教育の中で、彼らは、むしろ差別される側になってしまうのではないか、さらには、彼らを理解でき、それを評価できる人間も、一定程度資質を持つ者に限られるのではないか、こうした人々こそが、国家または社会にとって、成長の機関的役割を果たすのではないか、といったような疑問が生じることは避けられない。これらの疑問は、正に、前節に述べた「違和感」と関係するものである。